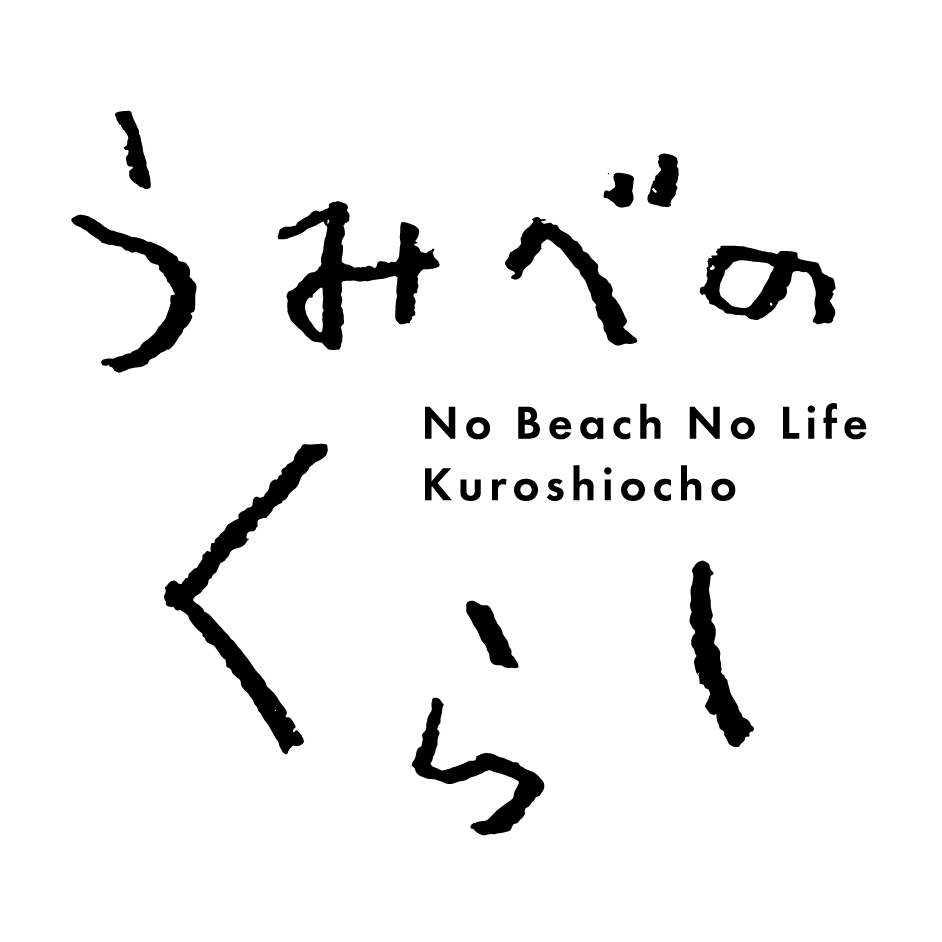増己さんのお父さんは鉄砲百合を作っていたそうだが、鉄砲百合は冷蔵庫で球根を保管したり、重いものを運ばなければならなかったりと、他の品目に比べて重労働であることから、増己さんは「何か新しい花を作ろう」と考えた。そこで出会ったのが今の主軸である「デルフィニウム」だった。
「農大の頃の同級生のいとこが芸西の方で花を栽培しよう言うてね。その人を訪ねる前は、『トルコキキョウを作りたい』と思いよって、でも、行ってみたらなかなか難しいと。それで、その芸西の人がデルフィニウムを作りよって、『野並さん、これやってみたらどうやろうか』いうことで始めたがよ。ブルーがすごい綺麗な花やけんね」


それから、芸西で出会った農家さんに育て方などを教えてもらいながら、デルフィニウムの栽培が始まった。ただ、栽培を始めてから3年間ほどは思う通りに育てることが難しかった。
「デルフィニウムの産地である高知の東の方の地域と田野浦では、土の質も違ったし、向こうは平野やけん、水の持ちが良かったり。田野浦は斜面が多いろう。全然条件が違うけんね。最初は作るのにすごい難儀したいうか、苦労したね」
毎年畑に堆肥を入れたりしながら、まずは土づくりから始めていき、ハウスの改修や芽かきの仕方の習得など、さまざまな勉強を重ねていきながら4年目、ようやく他の地域で出荷されているものと同等の品物が作れ始め、収入も安定していったという。
デルフィニウムの花は、9月から10月の間、3回に分けて植え付けをし、収穫は11月下旬から6月頃まで続く。一度植えれば次から次へと出てくる花だそうで、出荷が多い時期には早朝4時頃から作業をする。収穫したデルフィニウムの咲きすぎた「一番花」を取り除いたり、余計な草がついていればそれを取り、汚れを拭いたりして、そこからサイズごとに仕分けをして出荷に備えるという。

仕分けの作業場まで歩いて運ぶ

日々青く柔らかな花たちに囲まれ、一般的に言えば「癒される」ようにも思うけれど、四六時中デルフィニウムに囲まれている増己さんは、その状況を笑い話に語ってくれる。
「女房が本当に花が好きでね、家でも花瓶に挿すがよ。かすみ草を作りよる人らはね、ハウスで花を切りよう時にもかすみ草が揺れるけん、『夜寝る時に目瞑っても花がチラチラしよる』言うて、『もう、家では見とうない』と思うたりすると」(増)
笑いながら冗談を言う増己さんに、「嘘や、そんなの初めて聞いた」と反応する小寿枝さんは、花たちへの素直な気持ちをこぼす。
「デルフィニウムのこの色合いがね、なんとも。ほかにない色合いやんか。こういう色合いって、染めたりして出している花もあるけど、デルフィニウムは本当の色。この色に惹き込まれるでね」(小)。
これから先、忙しさが増す春の季節になると、弁当生活になる日々がやってくるという。そんな時、天気が良い日には2人で弁当を片手に、田野浦の人たちの間で「観音さん」と親しまれる飯積山へ登っていくという。

「この地域にずっとおっても『ここは素晴らしい』と思うところはね、観音さんから眺める景色。あれは最高。桜が咲いたらね、2人でお弁当下げてね、そこの桜の下のところへ食べに行く時がある。そこから眺める景色。すごい好き」(小)
忙しい時期ではあるのだろうけれど、束の間の休息の時間、春の暖かな陽を感じながら桜、田野浦の海、ハウス団地を上から眺め昼食をとるひと時は、「幸せ」以外のイメージが浮かび上がってこない。
そんな2人がデルフィニウムなどの栽培の傍、楽しみにしていること。それは、年に一度、子どもや孫たち計14人で出かける小旅行だという。
「ストックを植えちょうハウスでね、花の収穫が終わったら、ちょっと早めにスイカを植えるのよ。ひとハウス全部に。そのスイカの売り上げを貯めて、年に一度家族で行く小旅行。孫が6人、家族計14人、みんなで行く一泊旅行。それが一番の楽しみ」

花を抱く姿から本当に好きなことが伝わってくる。
田野浦という海辺の地で、花卉栽培をする農家は最盛期に比べ減ってきたという。それでも、2人の笑顔を見ていると、「花っていいな」という感情が自然と湧いてくる。
「持って帰り」と、ふわっと揺れるブルーのかわいい花を持たせてくれた。その花の中で2人の柔らかな笑顔が揺れ動いているように見えた。
野並増己さん・小寿枝さん
黒潮町田野浦地区でデルフィニウムをメインに花卉栽培を行う農家。デルフィニウム以外にストックや露地品目の栽培も行っている。県外市場への出荷がメインだが、規格外のものは町内にある「にこにこ市」や四万十市のJA グリーンにも出荷している。
text Lisa Okamoto