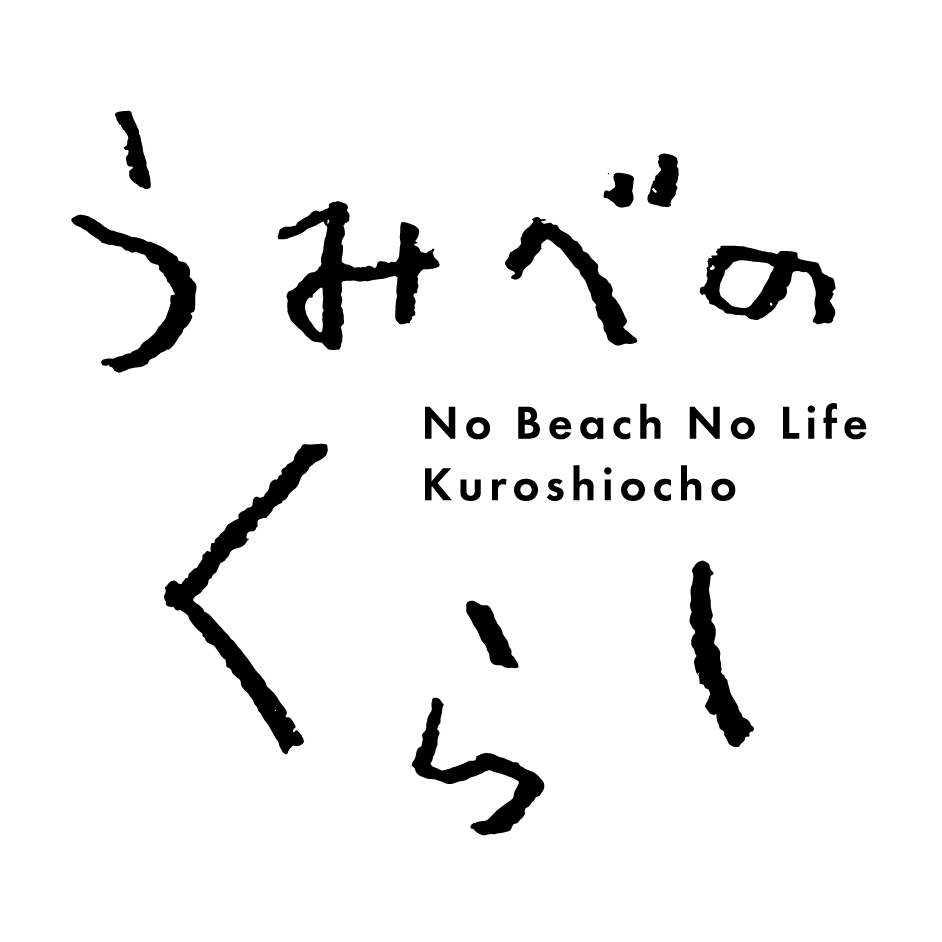「one two three ポイッ」
「自転車も一緒。3回やったらできるよ」
「自信持って」

「one, two three ポイッ」と可愛らしく表現し説明するブルースさん
日本語に簡単な英語が混ざり合いながら、リズミカルで優しいレクチャーの言葉が砂浜で跳ねる。
長く美しい浮鞭のビーチを前に、10年ほど前からサーフィンスクール「幡多サーフ道場」を営むディロン・ブルースさん(51)と妻・潤さん(50)。
オーストラリア出身のブルースさんが教えるスクールは、異国文化や外国人に慣れていなくたって、英語が喋れなくたって、なぜだか安心できて、いつの間にか海のとりこになってしまう。

ブルースさん自身がサーフィンを始めたのは、まだオーストラリアに住んでいた頃。
ゴールドコーストのお隣、ブリスベン出身のブルースさんは、海の無い地元からサーフィンを理由にゴールドコーストへ引っ越し、日本に来る以前にも現地でスクールを経営していた。
「その頃は日本人のお客さんがほとんど。でも、日本語が全然喋れないから勉強をしようと思って日本に来た。ちょっとだけのつもりが、今もずっと住んでるね」
24歳で初めて日本へ来て、最初は東京や湘南、大阪などに住んでいたけれど、都会はあんまり好きじゃなかった。そして、高知は良かった。
「都会は苦手。で、28年前、最初は四万十市。知り合いがいたから。それから10年後くらいに黒潮町。高知はすごく良い。波乗りと暮らしがとってものんびりで好き」
その頃の黒潮町は今よりももっとお店も少なく、交通の便も決して良いとは言えなかった。不便のように思うけれど、ブルースさんにとってはそれが良かった。オーストラリアの田舎と比べたら全然不便ではなかった。
妻・潤さんは、東京出身。2人はスクールの拠点である鞭で出会う。
「私、31歳の時にニュージーランドにワーキングホリデーに行ったんです。その時に知り合った日本人の友だちが須崎市の子で。で、高知の話になって「高知は行ったことがない」って言ったら、「それはもう、来ないとだめだよ」ってなって」
ワーキングホリデーの制度を利用できる年齢の31歳を目前にして、英語はほとんど喋れない中、渡航を決意。昔はシャイだったというけれど、誰も知らない異国の地の生活で自分の居場所を作っていった。
「関係ないんだなって思った。言葉は。昔は外国の人が来たら父親の陰に隠れてるような子どもだったんだけど、ちょっとオープンになったかな。本当に行って良かった」
日本とは季節が真逆のニュージーランドで充実した生活を手に入れた潤さん。向こうの夏が終われば日本に戻り、日本の夏が終わればまたニュージーランドへと帰る、”1年中夏”を過ごしていた潤さんは、東京へ帰国するも「なんだかもう東京には住めないかも」という思いから、その時、須崎の友人に連絡をとり、初めての高知へやって来た。
そして、友人が鞭の駐車場で紹介してくれたのがブルースさんだった。
「当時彼は今このスクールをやっている場所に家があって、ここに住んでたの。こんな目の前に海があって、朝海に入って、夕方また入って。ちょっとパラダイスじゃない?だから、その後一回東京に戻ったんだけど、また帰ってきたの」
山から海へ、潮風がふわっと取材中の小屋の中をくぐり抜け、ジリジリ光る風景に気持ち良さが流れる。

鞭の美しい海を望む絶好のロケーション

最初はそれぞれがともに移住者としてこの地に住み始めた2人。異国の地から日本に来たブルースさん。ニュージーランドで田舎の生活に慣れていたとは言え、日本の地方での暮らしは初めてだった潤さん。大変なこともあったかもしれないけれど、2人はそれを感じさせない。
「ブルースがこっちに来た20年前くらいはまだ外国の方も少なかったと思うし、最初は大変だったんじゃないかな」と潤さんが言えば、「そんなことない。そうでもない。Just surfingの仲間もいたしね」とブルースさん。
潤さんは潤さんで、「田舎暮らしって大変なのかなあって思う人もいると思うけど、私は一度ニュージーランドに行った経験から、好奇心というか、色んな人のことを知りたいっていうふうになってて、ハードルが下がってたかも」と話す。
2人に流れるポジティブで自然体なマインドがある。
それは、いつも2人の目の前にある美しい鞭の海がそうさせているのかも。

幡多サーフ道場
黒潮町浮鞭にあるサーフィンスクール。オーストラリア出身のディロン・ブルースさんが幡多弁や簡単な英語を織り交ぜながら指導するスクールはとてもやさしくて楽しい雰囲気。体験は11月まで受け入れ。要予約。ボードやウェットスーツのレンタルも可。不定休。
Text Lisa Okamoto