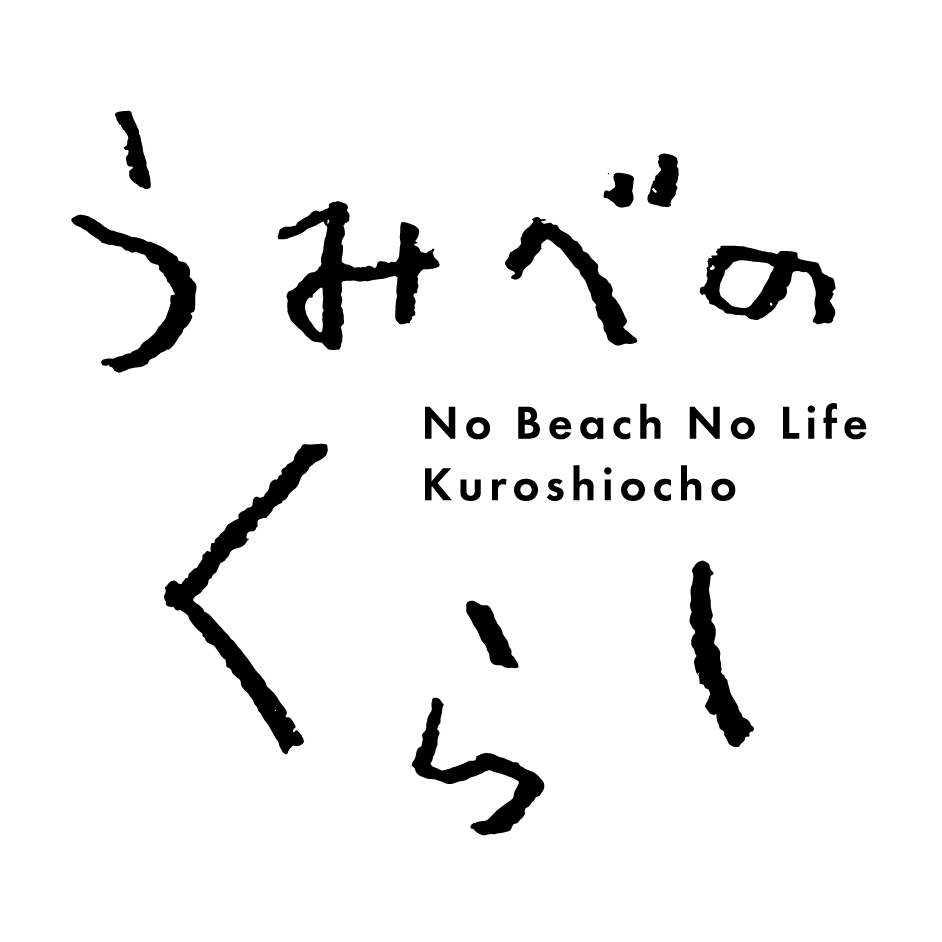「港町で育っちょうに、自分ら全然釣りとかせんし、漁師には全然憧れんかった。浜でも遊ぶけど、どちらかと言えば泳ぐのも川のほうが多かった。小さい時は、『漁師』っていうものをええようには思ってなかった」
「元カツオ漁師」という経歴を持つ喜多豊浩さん(40)は、28歳の時に黒潮町役場職員となり、現在13年目。佐賀支所にある建設課水道係で勤務している。

生まれ育った場所は、漁師町・佐賀の明神地区。カツオの一本釣りが有名な町で、父や親戚、近所のおんちゃんも漁師だらけという環境で暮らした。だからこそ、近くにあるからこそ、小さい頃は海や漁への憧れがなかった。
「昔は怒られたら『山に連れて行くぞ』なんて言われる家庭も多かったと思うけんど、『船に乗せるぞ』って言われちょった。『それだけは嫌』って」
喜多さん自身や周りの漁師の家庭にはそんな会話があったという。

高校卒業後、大学へ進学したけれど、家庭の事情により半年で退学。19歳で初めて自分の中に選択肢として浮上したのが「カツオ漁師」という仕事だった。
「家庭を助けるっていうのもあって。いとこのおんちゃんがカツオ船の船頭をしちょったき、その船に乗せてもろうた。嫌やったけど、乗るなら3年はっていう約束で」
でも、やっぱり荒波に揉まれることになった。
乗船して初めての航海。フィリピン沖で事故に遭い、顎に怪我を負った喜多さんは、水上ヘリで緊急搬送され全国ニュースにもなった。半年ほどのリハビリを終え、再度乗船するものの、先輩たちに怒られる日々。今でこそ、「300日乗っていたとしたら、700日分ばぁ怒られるがよ」と笑って振り返る喜多さんだけれど、当時はほとんど口を開かなくなっていたというほどしんどかった。
「そうは言っても、2年目くらいからは先輩にも可愛がってもらえるようになったり、ようやく楽しいところも出てきたりした。でも、まぁ若かったき。同級生たちは大学3年生で『就活が-』とか話したり、就活がない子は遊びよう。浮かれた話を周りでしている時に、自分の切羽詰まったような、生き死にがかかっているような状況がだんだんアホらしくなってきて」
「でも、漁師をやってよかったと思うこともあるがよ。父親がどれだけ大変な思いをして育ててきてくれたのかがわかった。命懸けのことをしてくれていたんだなって、今は尊敬と感謝の気持ちやね」
「3年間は」という約束の通り、船上で3年の生活を終えた喜多さんは船を下りる決断をし、その後は四万十市や大阪でいくつかの職を経験した。

24歳の頃、大阪にある派遣会社で営業職として働いていた喜多さん。同僚が次々と退職をしていく状況もあり、若い年齢ではあったものの支店のマネージャーとなり、部下を20人ほど抱えながら忙しく仕事をしていた。そんなある日、夜遅くまで続いた会議を終え、岸和田の近くを車で帰っていると、ふと波の音が聞こえたという。
「海は見てないがやけど、音が聞こえたがよ。運転しながら自然と涙出るしよ。『地元におりたくない』と思って出て行ったけど、やっぱり『帰りたい』って思うのはふるさとっていうことでね。でも、波の音を聞いただけで自分がそんな風になるとは思わんかった」
あの頃は、波の音がすることが当たり前だった。故郷を離れてからも、波の音が無くなっていることには何も感じなかった。感じなかったはずなのに、「ある」ことに気づくと、自分がそういう環境で育ってきたことを思い出す。
「『あ、ずっとこれ(波の音)に囲まれて生きてきちょったがや』って考えてしもうて、無性に帰りたくなった」
その約半年後、勤めていた会社を退職し、しばらくは大阪で暮らしていたが、故郷である黒潮町の職員採用試験へ挑み、合格。家族とともに地元へ戻ってくることとなった。
入庁以来3つの部署を経験してきた喜多さんだが、土木係や水道係と、土木分野以外の部署での経験はなく、専門職のように長年の経験を積んできた。
ただ、入庁前に抱いていた思いもある。
「職員として何がしたいかって考えよったら、『仕事がない』という課題があるなと。自分らも『帰ってきたい』と思いよっても、それまで帰って来れんかったって言うのは、仕事がなかったからやった。そういう思いもあったき、企業誘致ができたらとか、漁師の経験があるから、例えば水産業の分野でも少しは何かできるかなとか」
入庁当時の喜多さんは28歳。東京や大阪へ出て行った同級生たちの多くが、これから先もこの場所で生きて行くのか、地元へ帰るのか、人生の進路を一度は考える時期だっただろうと話す。自身も同じタイミングで地元へ帰る決断をしたからこそ、「仕事がない」から帰郷することを諦めるという選択を同級生がすることが「寂しい」と思ったという。
産業振興の分野での経験はまだないけれど、喜多さんが仕事をする上でいつも考えているのは、地域のおんちゃんおばちゃんのこと、同級生や後輩たちのこと、「人」のことだ。
「僕らは対住民さんの仕事をしているわけやけど、例えば困っちょう住民さんがいたとして、その人は昔小さい時から面倒を見てもろうちょうおんちゃんおばちゃんやったり、助けてもろうちょうおんちゃんおばちゃんやったりする。そういう時に、役場の職員として判断せないかんのは当たり前ながやけど、その人に対する返事をする時には、『役場の喜多豊浩』じゃなくて、『役場へ勤めよう昔から知っちょう喜多豊浩ですよ』っていう形の返事、関わり方をしたいなと思う」
佐賀という漁師町は、昔から家族や親戚、ご近所同士の距離がとても近く、濃いという。そんな環境で育ってきたからこそ、「役場の職員」である前に、この町に帰ってきたからこそ、「喜多豊浩」としてありたいのかもしれない。
「まぁ、どこまで行っても公務員ながやけどね」
そのことも理解しながら。

「黒潮町の魅力は」という問いに対しても、喜多さんの心は一貫して人と通っているところがある。
「人やと思うがよ。自分らは佐賀のこの、人との距離感がうんと近いところで育ってきちょうき、それがすごい居心地が良かったり、安心する距離感だったりする。ちょっと度が過ぎたフレンドリーみたいな感じもあるがやけど。『波の音が聞こえてここへ帰ってきたくなった』いうのも、この町に帰ってきたかったがか、この町の雰囲気に癒されたかったがか。多分、癒されたかったがやと思うがやけんど、じゃあ『町の雰囲気って何か』って言ったら、育ててくれたおんちゃんおばちゃんらがおって、町歩きよったら声かけられてっていう」
人と近い町、狭い町。昔はそれがすごく嫌だったと話すけれど・・・
「やけど、うん。そこがええところながやないかなって思う。人がおらんと町にならんし。やき、人が増えたり、帰ってきたい人には帰ってきて欲しいなって思う。佐賀に限らず、どこの出身の人でも一度は地元に戻ることを思うろうき、その時に『仕事がない』っていう理由でそれをやめるような感じじゃない町になってほしいと思う。『選択肢があるけど戻らないことを選んだ』、それならしょうがないよねって」
喜多さんが好きだという佐賀の港町の景色。
小さい頃は憧れていなかった暮らしや仕事も、船の上でのしんどかった経験も、故郷を離れ遠くの地で暮らしたことも、様々なことがあったけれど、心が落ち着き、心をざわつかせるのは、今、やっぱりこのうみべの景色。

「夜そこに立つと、なんかすごいこう。『ざわっ』とするというか。絶対に風が吹きよって。その風景が懐かしい」
その理由は、そこがふるさとで、そこに大切な人たちがいるから。ただそれだけのシンプルなこと。

人間味溢れる町の職員
喜多豊浩さん(40)
黒潮町役場職員。佐賀・明神地区出身。2011年に役場へ入庁し、現在13年目。まちづくり課土木係、建設課土木係を経て、現在は建設課水道係の担当として5年目。趣味はドラム。休日には地元のメンバーとバンドを組み演奏を楽しんでいる。
text Lisa Okamoto